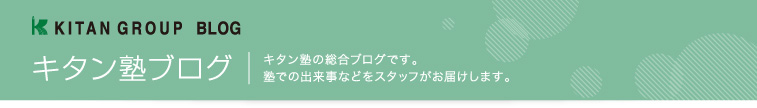
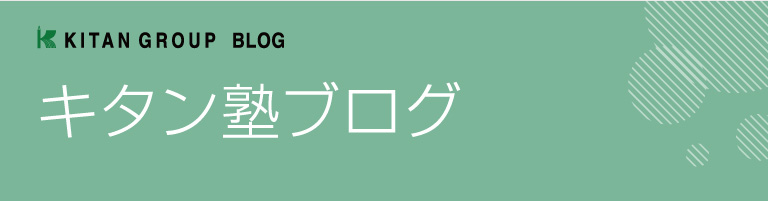
3月から、塾の新年度ははじまっていますが、新しい仲間を迎え、授業も本格的になって、中学部の補習もはじまり、……この4月が新年度はじまりと言ってもいいでしょう。学校の勉強もいよいよはじまりますし。
4月5日から授業再開です。残念ながらやめてしまった友達もいますが、新しい友達もたくさん入ってくれました。新しく塾に入る人は、今ドキドキしているのでしょうか。心の準備はどうですか。春休みは十分に休めましたか。光の泉の春期講習は今回早めに終わったので、講習に参加した人も、十分休めたと思います。
この新年度、まず何をはじめたらいいのでしょう。新中2や新中3のみなさんで気になるのは、やはり通知票でしょうか。今年の中2や中3には、「内申が悪い」ことで悩んでいる人が多く、心配しています。新しく中学生になるみなさんも、「通知票」「内申」という言葉をお母さんや塾の先生から何回も聞いて、恐れと不安の気持ちでいるかもしれません。
中学生のころはどうだったかなあ。わたしは梅林中学にいたんだけれども、内申はあまり気にしなかったなあ。「先生は内申よかったからでしょう」と言い返されそうですが、実際そんなに気にしてなかった。まあ、わたしの場合、幸いにも環境が良かったから、美術とか音楽とか技術家庭とかで苦労したことがなかった。
実家の親戚が「印刷屋さん」で、よく遊びに行っていて、幼稚園のころから、「色分解」のやり方とか知っていた。何せおじさん(父の弟さん)が、小さい私に、「色の三原色」の講義をしてくれ、「赤(マゼンタ)」「黄(イエロー)」「青(シアン)」ですべての色が作れるのに、なぜ「黒(ブラック)」を使う必要があるのか……とかいった、幼稚園の子にふさわしくないことまで、熱弁してくれた。刷りたてのプリントまで持ってきて。そりゃあ美術に興味を持つはずだ。
中1になったとき、数学の家庭教師が来たのだが、あまり教えることがなかったので、最後にギターを教えてくれた。その日の2時間のノルマを、だいたい1時間でこなしてしまうので、後半の1時間はほとんどギターのレッスンだった。おかげで、コードについては、新しく勉強する必要は全然なかった。ウチのばあさんは渋い顔をしていたが。
家庭科は……ふつう男の子は苦手なのだが、わたしの実家は注文洋服店。幼いときの遊び道具は、仕事場の空いている「ミシン」だった。
こうしてみると、すごい環境だったなあ。内申とるには楽な環境でした。ちょっと感謝(でも内申がとれたから幸せになるわけではないよ…)。
とはいっても、努力しなかったわけではない。いや、たぶん、主要5教科よりも勉強している。よく、主要5教科はよくできるが、残りの4教科はまるでだめ。という人がいて、「どうしたら内申がとれるのですか」とか聞かれることが多い。
どう答えればいいのだろう。授業を一生懸命聞きなさい(?)。努力している様子を先生にわかりやすくアピールしなさい(?)。あげくの果てに、質問をたくさんして、先生に取り入りなさい(?)。というのまであります。どれも、なんだかなあ……という答えです。
どうなんでしょう。「プロを目指しなさい」というのはだめですか。
実際わたし、イラストレーターになりたくて、中1のころ、レタリングの通信講座をはじめていました。本棚には、参考書よりも、「マンガのかきかた(石森章太郎)」「レタリング入門」「活字の見本帳」みたいな種類の本が多いくらいでした。
ギターのほうは、これこそ本気で、シンガーソングライター(なつかしいことばだ)を目指して、日々特訓していたのです。
実家の洋服屋は継ぎたくなかったので、洋服のプロは目指さなかったのですが、悲しいかな、身体がすっかり覚えていて、絵よりもギターよりもうまかったのが、「ミシン」の使い方でした。
プロを目指す。これ、本気で大切なことだと思います。だってねえ、今の世の中、何でも身につけていないと大変だよ。数学とか、英語とか、いくらできたって、それがそのままの形で役に立つ職業は、塾の先生くらいです(だから塾の先生には、世間的なことが何もできないおぼっちゃんが多いです。わたしはその筆頭です)。
なぜ学校の科目に、美術とか音楽とか技術家庭とか保健体育(今回この科目は出てきません…これだけはずっと3でした)を学ぶのか、よく考えてみましょう。
単なる教養を身につけるという意味もあるかもしれませんが、才能を見い出して、専門家を養成する……という意味もあるのではないでしょうか。
美術の先生や、音楽の先生には、かつて画家や演奏家を目指して、夢破れた人……みたいな人種がやっています。わたしも、かつては数学者を目指していて、夢破れた人です。たとえばわたしなんかも、数学のセンスがある生徒を見ると、結構かわいがってしまったりします(不公平だとよく反省しますが)。美術や音楽の先生もきっと同じ気持ちでしょう。プロを目指しているような生徒に、「5」以外の数字はつけられません。「10」くらいあげたい気分になるはずです。
なんかまたお説教モードになってきたので、話題を変えます。
この新年度は、わたしも慎重にいろいろ準備をしています。今いちばん考えなくてはならないのが、「からだの休め方」です。昨年度は体調面でみんなに心配をかけてしまいました。
サイトメガウィルス事件の前後で、移植腎のレベルが1段階下がってしまいました。クレアチニンという、腎臓の機能をはかる検査の値(健康な人で0.8とかだったりする)が、1.2~2.5くらいだったのが、3.0~4.2あたりをウロチョロしています。亡くなった智恵子さんが7.0とか8.0とかだったので、まだまだ先はある(ホントか)のですが、4.3とかの数字が出ると、ちょっと先が見えてきた気分になります。足のむくみはとまらず、60度くらいしかまがらなくなったので、今や足元の消しゴムすら拾えません。まったくもって情けない。
水分をちょっと取っただけで、頭がクラクラするようになったので、最近は水分量も気をつけています。どれくらいの水分が体に快適か、探っているところです。
前はこんなとき、隣にいる智恵子さんに聞けば何でも教えてくれたのですが(臨床検査技師だけに)、今は、部屋の温度をどうすればいいか、何を食べるといちばん体の調子が良くなるのか、という初歩的なことまでも手探りです。
でも、これは本気でがんばろうと思います。だってやはりこの仕事は好きだから。
何か月くらい前だったか忘れたけれど、谷澤先生に「先生の持っている光の泉のいろいろなもの(精神?技術?知識)を若い者に伝えてほしい。と頼まれたことがありました。
こんな風に言ってくれる先生がいるのは有り難いことです。
でも、私の持っているものっていったい何だろう。
採点はたぶん、光の泉でいちばん遅いし。仕事がテキパキとできるわけでもない。パリッとした恰好は当然できないし、このブログは猫のことばかり。ああ、いいところがない。
光の泉のカリキュラムを作る技術。あれには技術は全然いらない。いるのは、ひたすら単調作業に耐える能力だけだ。忍耐力……いやこれは伝えるものではない。
教室が多少うるさくても、一瞬で静かにさせる技術……いやこれは、単にわたしが「俺様キャラ」なだけで、塾の授業をしているときだけは、「俺様の授業でしゃべるとはいい度胸だな」モードになってしまうからで、自慢できることでは全然ない。最近はそれが浸透してきたので、怒る必要すらない。教室に入っただけで誰もしゃべらない。
よく、静かなクラスでは授業がやりにくい……とかいう先生がいるが、あの気持ちが全然わからない。たいていの若い先生は、生徒と対話しながら授業を盛り上げていくみたいで、それはそれで大切だろうから、私の授業はマネする必要はない。たぶんマネできない。
補習のやり方といっても、いつも気をつけているのは、目立つ生徒や無駄な質問する生徒は適当にあしらって、ひっそりとスミにいる生徒のそばでニッコリ笑いかけたりする。うるさい生徒のせいで静かにがんばっている生徒がじゃまにならないようにする。楽しい雰囲気の補習であっても、あえて悪役になって、その場を静粛にさせる。それくらいだ。
でもまあ、こんな基本的なことは、たとえば谷澤先生くらいだと、いつも率先してやっていて、それより若い先生がそれを見習ってくれれば、何も心配いらない。新年度は土曜日入らなくなったので、そんな「いい補習」が行われているのだろうなあ……と、うらやましくなったりする。土曜の補習は出たかったなあ。ちょっとそこは失敗した。
わたしのかつて作ってきた授業の規則といっても、「友達が変な答えを言ったときに「クスッ」と笑ったりしたら滅茶苦茶感情的に怒られる」とか、「テスト中に消しゴムを落としたとき、自分で拾ってはいけない。手を上げること」とかいった変なのばかりだ。おまけに最近はその消しゴムを拾ってあげることもできない。
光の泉の作業はすさまじいのが多いから、どんなちっぽけな作業でも「手伝わなくていいの?」のひとことを言う。作業がはじまったら、上下関係、年齢とかいっさい関係なく、いやむしろ役職が上の者、年齢が上の者が率先して行う……これかなあ。
でもこれは、どんな会社でも、どんな世界でも、当たり前のことだと思うし、谷澤先生、中林先生、鎌田先生、高橋先生、……とかの顔を思い出すと、みんなそんな当たり前のことは、当たり前のようにやってくれそうな奴らばかりだったりする。
おまけに今の私は力仕事は全然できないし、足元の消しゴムすら拾えない。
う~ん、谷澤先生が言っていた「伝えること」がひとつもない。これは弱った。
とにかく今は、「少しでも長く生きること」に全力を尽くそう。仕事が終わってからどんなマッサージをすると効果的か、一生懸命考えよう。どの温度で寝ると、明日の朝、だるさがいちばん取れるのか、いろいろ実験してみよう。スーパー栄養剤「若甦」を何日飲んで、何日休むリズムがいちばんからだによいか、いろいろ試してみよう。「からだの回復法」の専門家、プロになることを目指そうと思う。
どんな分野でも、必ずプロになることを目指す。伝えないかんことは、実はこれかなあ。
光の泉本校校長 松田 一哉