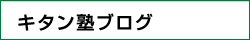

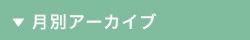

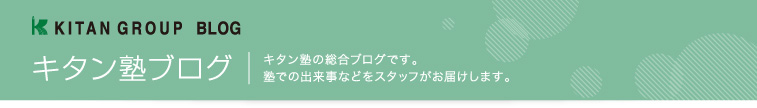
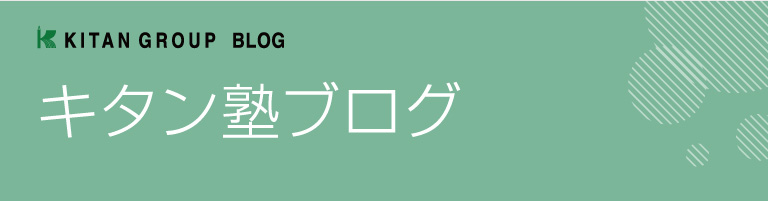
今、保護者の方との懇談をやっていて、その中で聞かれるのが、「先生、うちの子は、どうして成績が上がらないのでしょうか。けっこうまじめに時間かけて勉強をやっているのに」という、お母さん(またはお父さん)のセリフです。
この質問に対する答えはたぶん、その生徒の性格、生活環境、心がまえ、そして残念ながらもともとの素養(つまりお父さんかお母さんのどちらかが頭がいい)などがからんでくるので、一概に「こうだ」と絞ることはできないと思います。それこそ、そのために保護者懇談を個別に開いているので、そのときそのときの先生のアドバイスを大切にしてください…ということになってしまいます。
ただ、その代わりと言っては何ですが、ひとつだけ、まあまあ予測できる方法があります。それは、実際にお子さんのテストを採点してみること、もしくはお子さん自身に採点させてみること…という方法です。
今日も直前の特色化選抜の採点をしていていろいろなことがわかりました。このテストは、基本的に自己採点をさせ、それを回収し、作文や記述など、大事なところをこちらで採点し、自己採点のまちがいも同時にチェックする。といった流れです。当然、いろいろな採点のしかたが、各自で違っていて非常におもしろい。
● 「完答」と書いてあるにもかかわらず、それぞれに〇が打ってある。おまけにそれをそれぞれ点数にしてしまい、実際より高い点数になっている。今日もそれで、全部の点数を数え直してしまいました。
● 例えばこんな質問「…当時の武士はどのような生活を営んでいたか、館の周辺の様子を参考にして…」の答えが「武芸の訓練を行ったり、農民を使って農業を営んだりしていた」というように2つのことがらにまたがっています。これが片方しか書いていないとき、〇にする人、△にする人、☓にする人…と3種類に分かれます。
● 〇もうってあるし、内容もいいな…と思って読み直してみたら、なんか読みにくい。よくよくみたら、その文には読点がほとんど使っていなかった。
● 当然、採点は厳しいほうがよいと思うのですが、よくよく答案を読んでみると、答えの意味がよくわからないために、ちょっと表現が違っても☓にしてある。つまり、採点が厳しい答案は2種類あって、本当に厳しく、向上心がある答案と、明らかに勉強不足のため、厳しくせざるをえない答案にはっきり分かれる(しかもその区別は何となく採点していて分かります)。
● 「It begins in June.」のinがfromになっている。「in[during] the rainy season」のtheが抜けている。こんなときも、それを〇にしている答案と☓にしている答案がある。
● 作文は、人に読ませる文章を書くはずなのに、明らかに読めない漢字が3つも4つもまじっている。
適当に思いついた順に書いていっただけで、こんなにありました。どうもこのへんに「いくら長くまじめに勉強していても、成績が上がらない」秘密がかくれているとは思いませんか。もう中3の答案は、さすがに直前なので、あまり指摘することは避けましたが、中2以下のみなさんが、このことに気づいてくれたら、たぶん勉強時間はもっと少なく、ぐんと伸びていくはずなのです。
つまり、テストは人に採点してもらうだけでなく、お子さん自身に採点させ、それをチェックすることで、だいたいどんな感じに勉強しているかが、浮かび上がってくるのです。
この方法は単純でよくわかるのですが、意外と実行しにくい(自分で採点するとよい、月例や週テストは、すでに採点してあったりするから…)のが欠点です。これをいちばん経験しているのは塾の先生なのですが、たとえそれを質問したとしても、塾の先生もすべての答案を覚えているわけはないので、当然アドバイスは一般的なことで終わってしまいます(その子の答案のようすを覚えているフリくらいはできますが…苦笑)。
もしちょっと時間をさけるのであれば、どこかでテスト用紙を手に入れてやってみてください。その際、選ぶテストは、①全範囲が習ったところばかりであること。②全体的にやさしめであるが、記述がやや多く、採点が迷いそうなものであること。くらいに気をつけるとよいでしょう。ない場合は、全国の公立の入試問題で、習ったところをコピーしてやらせるのがよろしいかと思います(ただしこれは当然ですが中学生以上です)。
たぶん自分のお子さんの、勉強のやり方が手にとるようにわかると思いますよ。やった答案を、そのままコピーして、親子でそれぞれ採点してみても面白いですね。
本校校長 松田 一哉