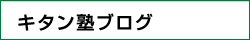

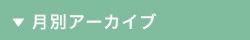

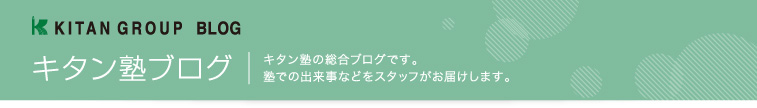
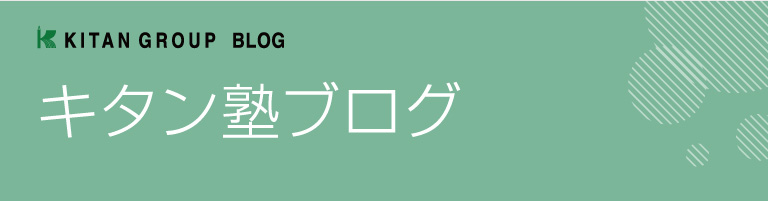
今日は岐阜大学附属病院で再検査があり、2.4あったクレアチニンが1.9までもどりました。夏期講習の前なので心配でしたが、これで何とか、講習は乗り切れそうです。しかし、これにより、今回の原因が猫であることがはっきりしたため、移植外科の先生に相当きつく注意されました。「そもそも腎移植患者は、動物は飼ってはいけない。鳥は絶対にダメ。犬や猫も、本当はダメです。それで命を落とす人もいるからね」
反省しつつも、これで夏期講習がしっかりやれることがわかり、嬉しくて帰りにとんかつ(1380円)食べに行きました。
ところで、先週の日曜日、7月3日に、名古屋市の愛知工業大附属中学校に行ってきました。そこで、E-BEST小6の生徒の模擬試験(滝をはじめとする有名私立中学入試用)があり、同時に「中学受験をめざしている生徒の夏の過ごし方」という題名の講演会を傍聴してきました。
1時をまわったころ、ようやく小6の4人がそろい、子供たちは試験会場に。保護者の方は地下の講演会場に案内されたので、私もその会場に向かいました。
前半の1時間は、代表の方のあいさつと、愛知工業大附属中学校の宣伝で終わってしまったので、ちょっとがっかり。後半もこんな調子では、お母さん方にわざわざ来てもらった意味がない。ドキドキしながら後半へ。
しかし、その心配は杞憂に終わりました。お客さんのほうは、必ずしも「熱く」というほどではなかったのですが、前に立った4人のパネラーたちは、同じ「塾講師の匂い」がする話ぶりで、とても楽しい時間が過ごせました。
もともと、塾講師になる人間というのは、「勉強すること」と「それを教えること」に関しては、異様な自信があり、逆に「それ以外」のことはまったくできない。もしくは、それ以外のことは「そつなく」こなせるけれども、秀でたものではない。みたいなタイプが多く、そのことが何がしか「コンプレックス」になっていたりします。
そういう屈折した人が、こうした「発表」の場を与えられると、ふだんとは考えられないほどテンションが上がり、「いつもと違う自分」が完成します。
今回の4人のパネラーたちも、まさにそんな「高い」テンションの状態で、立て板に水のごとく、「夏休みの過ごし方」についての持論を展開してくれました。
その内容に深くこの場で立ち入りたいところですが、あまり詳しく書いてしまうと、その団体の「企業秘密」の部分までばらしてしまうことになりかねません。
その人たちのいろいろなアドバイスを、私なりに解釈し、私の言葉に直して、その会場の雰囲気を伝えることができればと考えています。
まず、最初に思うのは、その「真剣さ」です。光の泉にいて、保護者の方と懇談したり、生徒と話したりしていると、「安易な夢」を聞くことがあります。
例えば、「医者になりたい」とか「弁護士になりたい」といった希望です。最近では、「医者になりたい」が最も多く、5人に1人の割合で聞くこともあるくらいです。
でも、その実、そうした人たちが(そうした人の親たちが)、それに向けて真剣に努力しているのか……と言えば、そういう人に限ってほとんど何もしていない。
その人たちにこの様子を見せてあげたいな。今回は第1回ということもあり、あまり熱を帯びるほどではなかったのですが、どの親もしっかりメモをとっていましたし、子供たちも、試験の直前まで、表情は硬く、このあとの試験に向けた集中力は、光の泉の統一テストの緊張感のなさと比べるのも悪いほどです。
さて、次はやはり「夏休みの過ごし方」についての本論です。これは、先ほど触れたように、あまり細かいところまでは述べられませんが、大きく考えて、「高校入試と中学入試の違い」「国語の重要性」「夏はどこまで仕上げるか、その計画の立て方」の3つで話が進んだ感じです。
「高校入試との違い」に関しては、実際にそのテーマで話があったわけではありません。「岐阜高校に受かるために」この何十年かやってきたことと、ついつい比べてしまっただけです。
高校入試というのは、ある程度目標が定まっていれば、少々まとはずれな方向に進んでしまっていても、「無駄」にはなりません。それが「いぶし銀」のように、力を発揮することもあるので、無理に「最短の道」を歩む必要はないのです。特に「公立高校の入試」は概して簡単なので、努力があらぬ方向を向いていても、あとで修正がきくのです。
ところが中学入試は、「もともとその子供がせいぜい小学6年生である」という事実から出発しています。あれもこれも一般的なことをやれば頭に入るわけでなく(もちろん特別頭がいい場合は別です)、その勉強法でやっていくと、「ゴール」にたどりつかないのです。
ゴールがどの志望校であるか…が出発点で、少なくとも指導者は、その志望校の入試を何年分か調査し、その傾向を十分に把握し、「最小の努力」でその道にのせていけるように、「指導者と保護者」が導いてやらなくてはならないのです。
高校入試だと、「自分でひとり立ちできる」ことが大切で、少々荒っぽい言い方をすれば、塾講師が途中ところどころさぼっていても、「自分の勉強のやり方」が見えた生徒であれば、放任してもよいのです。
ところが、中学入試だとそうはいかない。ゴールまで、100%ぎりぎりで持っていく必要がある。もともと「受かるぎりぎりの能力」しかない生徒、「このまま突き進んでいても受からない」と思われる生徒を、100%ぎりぎりで合格させるのだ。高校入試のように、120%くらいの余裕の力を持って受験する。といった方法が取れるほど、子供が成熟していないのだ。それには、保護者の方の努力はもちろん、塾の講師の力量が大切になってくる。漠然と授業する…だけでは、とうていそこに到達しない。
国語については興味があった。もともと高校入試では5分の1の割合で考える科目。それが、この5~6年は「特色化ブーム」で、国語の重要性が問われていた。しかしこれも今度の変革で、一過性のブームで終わる可能性がある。
ところが中学受験の国語は4分の1。しかも残りの3科目である、算数・理科・社会はある程度中学受験勉強をしっかりやった子にとっては、ほぼ満点に近く持っていけるため、点差があまり開かない。国語のみが計算できない科目。その重要性は、当然ダントツだ。
高校入試だと、ある程度の国語力があれば、それを「慣れ」と「練習」で、ある程度合格ラインに持っていける。よく、新聞のコラム(朝日の天声人語や毎日の余禄など)や、社説などを読むことで国語力が上がるというが、高校入試の場合、そうした根本的な解決も大切だろうが、それよりも実際の入試問題にあたって演習したほうが、効果が上がったりする。
しかし、中学入試の場合は、その新聞のコラムや社説、エッセイなどを読む…もっと極端に「写す」だけでもよいと言い切る。そこがすごく新鮮であった。ある意味、中学入試のほうが、高校入試よりも国語力がいるということであろうか。
これを今の6年生に応用しようとするならば、ただ「新聞のコラムを読んだほうがいいよ」で済ませてはいけないであろう。朝日などの全国紙の新聞に目を通し、小学生でもわかる話題のとき、それを生徒に読ませ、写させるまでやるべきであろう。それも、大きめの原稿用紙を用意して、(特に字が汚い生徒を救うためにも)しっかり写したかどうかをチェックする。そこにある漢字や難しい語句の意味をきちんとさせる。そういったことを手取り足取りやって、内容をどれだけ理解しているか、できるだけ詳しく説明させる。そこまでやらないと、効果は1つも期待できないでしょう。
最後は、夏休みの計画の立て方について。中学受験の場合、ただ漠然とカリキュラムをならべ、それを機械的にやらせることは、非常に危険であり、効果も少ない。不幸にしてそうしたカリキュラムしか立てられない場合は、それぞれの講師が、本人たちの志望校の入試問題を研究し、その相当ページの、どこを中心的にやっていくか、どこはやらなくてもいいか、など、問題番号まで指定できる必要がある。
また、冬休みまでにこれだけ理解させるのであるから、夏休みにそのうちどれだけこなすのか考える…などなど、中学入試には、「ゴールからさかのぼって」という符号がよく登場する。
でもまてよ。こうしたことは、実は自分が新人のとき、当たり前のようにやっていたことに気がついた。当時の予習したテキストを読むと、「これは重点的に」「これはやらなくてもよい」などの書き込みがびっしりしてあったりする。
最近できているのか。その答えはNoと言わざるを得ない。
そんなこんなで、忙しい1日が終わった。問題はそこで得たことを、さっそくこの夏休みから、反映できるかどうかにかかっている。
光の泉本校校長 松田一哉