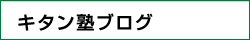

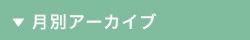

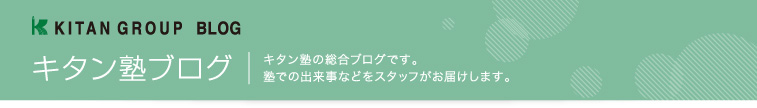
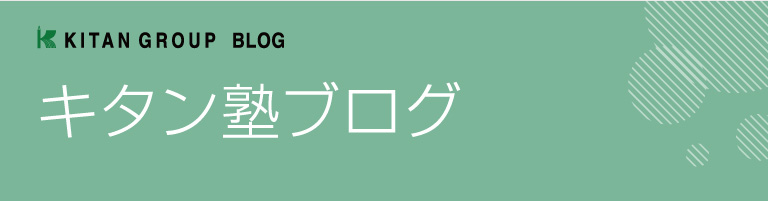
今週あたりで、学校の定期テストが終わる学校は多いみたいですね。テストが終わってほっとしたところでしょうか。どうでした。まあまあの点数は期待できそうですか。光の泉にいると、こういうとき、たいてい「5教科で450点取れれば合格だね」と言われます。
1科目90点以上。それは無理だよ…という声が聞こえてきそうです。特に光の泉では、手取り足取り「定期テスト対策」するわけでもなく、理科や社会など、学校と違う順番でやっていたりしています(理科でいうと、中2は「動物」をやっていたので、学校で「電気」やっている子はたいへんだったろうなあ。中3は「細胞と遺伝」「力のはたらき」あたりはカバーしたけれど、「イオン」までは触れていない…などなど)。
他の「親切な」塾に比べて、とても「不親切な」塾だから、その上「450点はふつうに取ってね」なんて言われたくない…って思っているかもしれません。
「不親切な」部分については、光の泉のほうも反省する点は多いかなあ。さすがにこの時代、もう少しサービスしないと、「ついていけない」→「やってられない」→「ほかの親切な塾に変わろう」ってことになりそうです。

ときどき、中学生の授業などでしゃべったことはあるのですが、私の小学校、中学校時代は非常に暗い青春でした。家には、「教育に命をかけている」おばあちゃんがいて、家にいるときは、食事以外はほぼ勉強をさせられました。定期テストで、必死に480点以上取って、やっと「今回は合格」みたいなことを言うおばあちゃんでした。えっ、あなたのうちのお母さんもこんな感じですか。それは辛いですねえ。90点を切る科目があった日には、家に帰れそうもなかったのです。それほどこわい人でした。
4歳のころに腎臓病(慢性腎炎)になっていて、中3になる少し前に、それが慢性腎不全になってしまい、緊急入院→人工透析→腎臓移植の手術という、腎臓を患っている人のお決まりのコースをたどりました。そのときからはさすがに、あまり「勉強しろ」とは言わなくなったのですが、私自身に「勉強していないと不安」という「刷り込み」がなされていたため、「勉強しろ」と言われなくても、そこそこ「勉強していた」気がします。
うちの嫁さん(高校1年生のときの同級生の佐野智恵子さん)がよく言っていました。「IQを比べれば、絶対私のほうが勝っていた(実際はかったとき、彼女にたいそう負けていました)。でもあなたみたいに、あれだけずっと勉強し続けることは私にはできないねえ。勉強し続けることも一種の才能だからねえ。」
まあ、裏を返せば、もっと頭がいい人なら、そこまで勉強しなくてもいい点数が取れるわけなので、私にはそんなにいい「才能」はなかったことになります。実際、大学合格という目標に関して言えば、彼女に「勝つ」ことができたのですが、一生をふりかえってみると、どう考えても、うちの嫁さんのほうが、「学業」も「私生活」も、充実した人生を送っていますしね。

私みたいに「黄信号」の子は、光の泉にはたくさんいそうです。「黄信号」の子というのは、ソコソコの才能はあっても、厳しく言わないと、なかなか勉強をやり出さない子。ちょっとやると、ググッと上がるくせに、その次の回にはすぐさぼってもとの順位にもどってしまう子。「厳しさ」という「緊張感」を常に与え続けていて、はじめて「青信号」の子と同じ位置まで登れる子。
この「黄信号」という言葉は、昔むかし、関西のほうに「伸学社」別名「入江塾」という「塾」があって(ラサール石井が通っていたことでも有名)、そこの学長の「入江伸」という先生が作った造語です。

光の泉には、あまり厳しい先生はいない。怖い先生もいない。私のことを「怖い」という生徒はいそうだが、実はそんなに厳しくないし、怖くもない。長くつきあっている子は、結構いいかげんなことも知っている。もっと厳しくて、きちんとしている先生はいるのだが、それでも「ソコソコ」厳しいレベルです。
うちのおばあちゃんや、その「入江伸」先生の、十分の一くらいかなあ。たぶん君たちは、まだ本物の「厳しく怖い」先生に会ったことがないと思います。

「青信号」の生徒は、ある程度「楽しい」授業をしても、関係なく「伸びて」いくでしょう。逆に「赤信号」の生徒を「ソコソコ」伸ばそうとするとき、「楽しさと怖さ」を混ぜた授業(アメとムチ)が有効です。
でも、「黄信号」の生徒はダメです。ましてや、「黄信号」の生徒を「岐阜高校に入れたい」と思うなら、「厳しく、怖い」緊張感を、「3年間休まず」張りつめさせなければダメです。
「厳しく」という定義にもいろいろあります。私のずっと前の授業がそうだったのですが、「自分の教え方」を「押し付ける」厳しい授業。それができないと、できるまで延々と「押し付ける」授業。それが「厳しい」ことだと勘違いしていた時期がありました。当然、話は面白くない。名古屋で塾を開いていたとき、このやり方で人数を半減させたことがあります。

実は、うちのおばあちゃんに勉強の話をさせると、非常に面白かったし、入江先生の授業も、「数学の海」「英語の海」を泳いでいるような授業…という伝説が残っています。
本当に厳しいという人は、実は「自分の勉強」は楽しく取り組んでいます。そこには、「自由闊達」な精神が常に流れています。
その先生の前に立つと、自分の心のゆがみが(立つだけで)、見えてきて、澄んだ心になれる。その先生の前に立つだけで、「ああ、もっと私は勉強しなければならない」「何事にもまじめに取り組まなくてはならない」と、自然に思わせることができる。
私自身が、「黄信号」な生徒だったので、永遠に「黄信号」な先生にしかなれないのではないか。常にそんな不安があります。ましてや私より優しい先生は、ほぼ「赤信号」な先生だろうと思います。
ウチの塾の方針の中に、「厳格さと愛情の教育」というのがあるのですが、「厳格さ」をもっている先生が何人いるのでしょう(私の基準では、私も含めてひとりもいない)。
私生活がほんの少しでも乱れている先生は、それだけでもう失格。私も名古屋にいたころ、そんな時期がありました。そういう人が「子どもの教育に命をかけている」と言っても、むなしく吠えているとしか映らない。説得力が全然ない。

ここしばらく、「凛」としたものを感じる人に会っていない。ウチの嫁さん(佐野智恵子さん)を世話してくれていた、ヘルパーさんのひとりの尾関さん。透析クリニックの看護師のチーフの竹下さん。訪問看護のリーダーの古田さん。そうした日々患者の死と向き合っている、医療スタッフの中には、何人かいました。
智恵子さんによると、医療スタッフの中にも、どうしようもない人たちも何人もいたそうですが…。ひとつのグループ、組織の中に、「凛」とした人がひとりいればいい方…くらいの割合だそうです。
そこにいくと、教育関係者はもっとダメだなあ。塾の先生になる人で、そこまで「凛」としたものを感じる先生に、ほとんど会っていない。ひとつのグループ、組織の中にひとりもいないこともざらにあります。医療スタッフの場合、ミスすると、患者は死んでしまうけれど、教育の場合、ミスしても生徒は死なないしねえ。緊張感が全然ちがうからねえ。
昨年私は、自分のミスで自分の嫁さんを死なせてしまいました。もう少し、もう少し緊張感があれば気づいたはずです。智恵子さんのほんのちょっとした体調の変化を見逃してしまい、気づいたときには彼女は死んでしまったのです。後悔しても、彼女が生き返ることはもうできないのです。

光の泉という塾がもっとすばらしい塾になるためには、光の泉の生徒たちがもっといい生徒になろうとするためには、光の泉の先生ももっといい先生になろうとするためには、何を考えなくてはならないのでしょう。
「黄信号」の先生が、「黄信号」の生徒を教えている今の状態。それではいい塾にはなれません。先生も「青信号」をめざし、生徒も「青信号」をめざす。それには、今、生きている「生」というものを真剣に考え、「真剣に生きる」ということを、「先生」も「生徒」も考えなくてはなりません。
「日々真剣」どんなときも張りつめている状態。身の回りにあふれている情報を、きちんとした心で受け止める。そして、「理解できるもの」「理解できないもの」に分けておいて、その日のうちに、「理解できないもの」には、自分なりの解決をつけ、「理解できるもの」は、徹底的にその理解を深めておく。
それができていれば、実は学校の定期テストで480点を取るのも、そんなに困難なことではないと思います。実際、ばあちゃんに、毎日そういう状態にさせられていた私が言うことだからまちがいないです。「させられていた」部分が「黄信号」なので、胸を張って言えることではありませんが…。
今日の話、だんだん観点がずれていってしまい、このままだと、「キリスト」や「ブッダ」レベルまで引き上げないと、よい先生、よい生徒になれない…あたりまで行っちゃいそうなので、このへんにしときます。
光の泉本校校長 松田 一哉