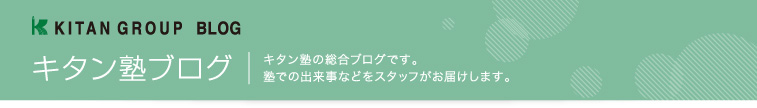
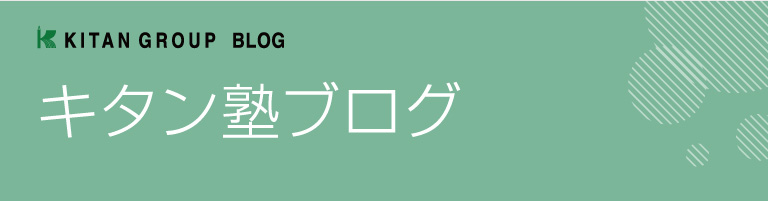
こんばんは。青木です。
歴史散策3を書かねばならないのです。実は、おとといにはアップしておかなければ」ならなかったのですが、一昨日・昨日と中間期末テスト対策をずっとやっていたので失念していました。すみません。だれも待っているわけではないからいいかな?いやいや、本科コースの先生たちで分担して書こうと決めたことですから、ついつい忘れてました、ではいけませんね。
あまりたくさんは無理ですが、今日も少し信長周辺に触れてみることにします。
前回、本能寺について少し書きましたが、本能寺の信長を襲った明智光秀のルートを一度たどってみたことがあります。当初の目的は、城をめぐっていたころなのでその一環として福知山城に行くことでした。ところが、京都南インターで降りて北西の丹波方面に車を走らせているとき、あっ、この道は光秀が丹波亀山城(現在は京都府亀岡市)から本能寺に向かった逆のルートだということに気付きました。ただでさえ、京都や奈良を走るときは次々に史跡が現れるのでわくわくしながら運転してるのに、光秀の本能寺ルートと知って胸はバクバクし出しました。鳥羽方面から、京都外大西高校を左に見て坂を登り始めました。登りきったところが「老ノ坂(おいのさか)」です。亀山からこの坂まで南東に進んできた光秀勢が右(つまり南)に行かず、左(ほぼ真東)に進路をとり、ひたひたと京の本能寺を目指したのです。この坂の上で、光秀は「敵は本能寺にあり」と呼号したことになっています。老ノ坂は、子供のころ信長の伝記を読んだときから一度は行ってみたい場所でした。感慨深かったです。
本能寺には中学生のときに行きました。ただし、場所は信長のころとは違うそうです。信長のころの本能寺の場所には行ったことがありません。中学のころに行った本能寺の近くには、今はない「京都花月」があって吉本新喜劇」の看板があったような記憶があるのですが…。
子供のころに読んだ矢田挿雲著の「太閤記」には、光秀方の家来として安田作兵衛や四王天但馬(しのうてんたじま)などの豪傑が描かれていましたが、その後大河ドラマや歴史ドラマにはさっぱり出てきません。あれは、矢田挿雲の創作キャラだったのかとも思い、それにしても安田作兵衛はまだしも四王天但馬とはすごい名前だったなあと思いながら、先日ネットで調べてみたら、やはり実在の人物たちでした。光秀の重臣・斎藤内蔵助利三(さいとうくらのすけとしみつ)の配下だったようです。安田作兵衛も四王天但馬も、信長に槍をつけた豪の者だそうで、信長は二人によって手傷を負い、自害を決めて奥にひっこんだようです。四王天但馬は、光秀が秀吉と覇権をかけた山崎の合戦で討ち死にしたそうですが、安田作兵衛は関ヶ原近くまで生き延びていたようです。
今日は、本能寺の変の大筋から外れて、ほぼだれも知らないだろう光秀の家来たちの話になってしまいましたが、次回はもう少し有名な斎藤内蔵助利三と明智左馬助光春(あけちさまのすけみつはる)について語ります。え?二人とも知らない?じゃあ、次回知ってください。