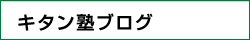

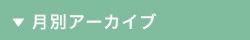

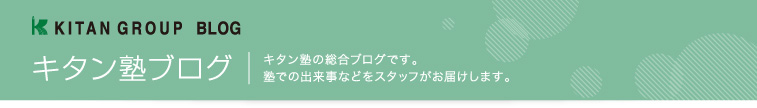
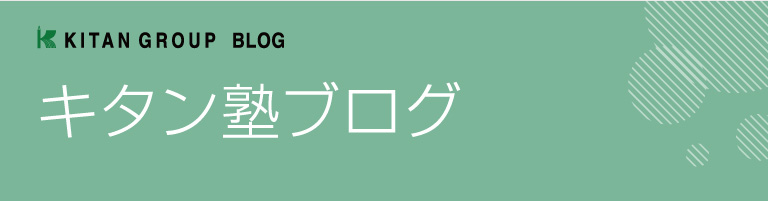
先週、光の泉の次年度のからの方針として、「光の泉本校、第2光の泉、光の泉北校、どの校も光の泉です。」という題名で、「光の泉本校、第2光の泉、光の泉北校の3校に、いろいろな先生を配置し、光の泉のどの校に入っても、同じスタッフで指導が受けられる」という内容の話を書きました。
この校なら「〇〇先生」とイメージできるほど、それぞれの校の先生に慣れ親しむことは良いことです。しかし、あまり同じ先生ばかりに教えられていると、仲良くなり過ぎてしまい、極端な話、その先生の指導でないとしっくりとしない、わからない…狭い窓口しか持てない人間になってしまいます。
将来、勉強に関して「プロ」になり、本物の人間になろうと思うのであれば、いろいろなタイプの教え方の先生に出会い、自分の窓口を広く持つことが大切です。幸い、光の泉の講師陣は、様々なタイプの、特色のある教え方をする先生がそろっています。来年度からは、この校はこの先生で決まり…みたいな安易な配置は行わず、3校が均等に、自由な発想でいろいろな先生に教えてもらえる光の泉になるように考えていきたいと思います。
「光の泉本校、第2光の泉、光の泉北校、どの校も光の泉です。」
この文章は、来年度からの改革の、他の流れにも共通して言えます。来年度の方針のメインとなる文章と言ってよいでしょう。
もともと、第2光の泉の練成コースは、光の泉の入塾試験に合格できなかった生徒が再チャレンジするために、しっかり基礎から勉強し直そうという講座でした。光の泉の入塾試験は受けずに、基本をやり直すため、最初から第2光を選んでくる生徒もいました。
第2光の泉で頑張って、半年から1年、みっちりと鍛え直し、再び、光の泉の入塾試験を受けて本校に入る生徒がいる。逆に、光の泉に入ったはいいが、順調に成績が伸びず、基礎からやり直すために、第2光に転塾する。そうした、「第2光の泉→光の泉本校」「光の泉本校→第2光の泉」の入れ換えが頻繁に起こることが、クラスの緊張感を高め、より競争の激しい世界で鍛えられる。第2光の泉はそういった役割を果たしてきました。
しかし、最近は、細々と「第2光の泉→光の泉本校」が、年に1回ある程度。「光の泉本校→第2光の泉」に至っては、ほとんどそのような例はないと言ってよいでしょう。
最近いちばん気になっていることは、特に本校で、A2(B)クラスから、なかなかA1(A)に上がれない生徒が、もう上のクラスに上がることを諦めてしまい、「どうせこれ以上落ちることはないのだから、のんびり通えばいいや」という姿勢になってしまっていることです。
その結果、どうなったのでしょう。最近それを確かめるため、統一テストの順位表を、第2光の泉と本校を混ぜて出してみました。すると、面白いことに、第2光の泉の平均点と光の泉本校の平均点が、さほど離れていないことがわかりました。本校の下位の5人くらいは、第2光の泉の練成コースの生徒に、明らかに負けているのです。
これは本来、あってほしくない状態です。せっかく光の泉の難しい選抜試験を突破したのに、中でサボり続けた結果、選抜試験を受けていない(もしくは受けたが受からなかった)練成コースの生徒より下の成績になってしまったのですから。もちろん、練成コースの生徒たちが、非常に頑張っていることも理由の1つでしょう。
こうした問題を解消し、再び、良い緊張感を取り戻すために、「第2光の泉→光の泉本校」「光の泉本校→第2光の泉」の入れ換えを活発にしようというのが、光の泉の改良点の2つめになるでしょう。
そのためには、校舎も、本校の校舎(別館・本館)と第2光の泉の校舎をあえて区別する必要はありません。1つの大きな「光の泉」という校舎と考えれば、A1(A)やA2(B)クラスの授業を第2光の泉の校舎で行ってもいいわけですし、逆に、第2光の泉の練成コースの授業を光の泉本校の校舎(別館・本館)で行ってもいいはずです。
実際、本校の校舎では、「山の手英才教育」や「高等部」の授業が入ってきたため、教室が手狭になっているという問題もあります。第2光の泉のきれいで広い校舎も十二分に利用していくために、教室もこだわらず、できるだけ、指導が円滑にいく場所で、よりよい環境が保てる場所で勉強ができるよう、配慮していこうと考えています。
これで光の泉の改良点、その2を話し終わりました。次回はその3(?)について話しましょうか。
繰り返しになるかもしれませんが、11月の初旬に行われる「保護者会」で、こうした重要事項、変更事項を発表したいと考えています。今回は、大切な保護者会となりそうです。もうすぐ案内を出しますので、よほどの用事がない限りは、万事繰り合わせの上、ぜひご出席くださるよう、お願い申し上げます。
光の泉校長 松田 一哉