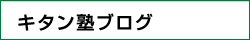

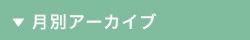

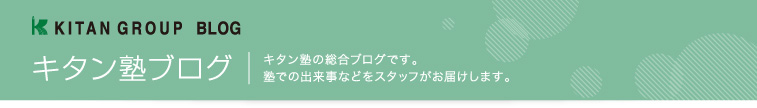
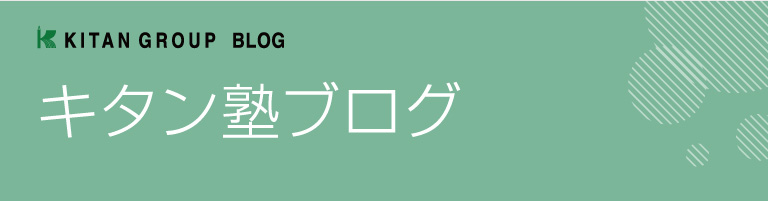
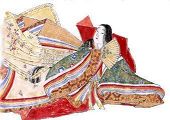 平安の才女 清少納言
平安の才女 清少納言
『枕草子』は約320段の章で構成されている。
『源氏物語』を貫く精神が“もののあはれ”(情感)の「静」とすれば、
『枕草子』には“をかし”(興味深い)という「動」の好奇心が満ちている。
作中には、実に400回以上も“をかし”が登場する。
この気持ちこそが、鋭い感受性で鮮烈に平安朝を描き出した清少納言の原動力だろう。
さて、その『枕草子』から、いくつか「~なもの」を現代語で書きならべてみた。
↓ ↓ ↓
第123段 はしたなきもの…きまりの悪いもの。
・他人が呼ばれているのに、自分と思って出てしまった時(贈り物を持ってる時はなおさら)
・何となく噂話のなかで誰かの悪口を言った時に、幼い子どもがそれを聞いて、当人の前で言い始めた時。
・悲しい話をされて本当に気の毒に思ってこちらも泣こうとしているのに、いくら泣き顔を作っても一滴も流れない時。
第135段 退屈を紛らわすもの
・碁、すごろく、物語。
・3、4歳の子どもが可愛らしく喋ったり、大人に必死で物語を話そうとして、途中で「間違えちゃった」と言うもの。
第146段 かわいらしいもの
・瓜にかいた幼子の顔。
・雀の子に「チュッ、チュッ」と言うと、こちらに跳ねてくる様子。
・おかっぱ頭の小さな子が、目に髪がかぶさるので、ちょっと首をかしげて物を見るしぐさ。
・公卿の子が奇麗な衣装を着せられて歩く姿。
・赤ちゃんを抱っこしてあやしているうちに、抱きついて寝てしまった時。
・人形遊びの道具。
・とてもちっちゃな蓮の浮葉。
・小さいものは何でも。
・少年が子どもらしい高い声で懸命に漢書を読んでいる様子。
・鶏のヒナがピヨピヨとやかましく鳴いて、人の後先に立ってちょこちょこ歩き回る姿。また、親が一緒になって走る姿。
・カルガモの卵。
・瑠璃の壺。
第147段 人前で図に乗るもの
・親が甘え癖をつけてしまった子。隣の局の子は4、5歳の悪戯盛りで、物を散らかしては壊す。
親子で遊びに来て、「あれ見ていい?ね、ね、お母さん」。大人が話しに夢中だと、部屋の物を勝手に出してくる。
親も親でそれを取り上げようともせず、「そんなことしちゃだめよ、こわさないでね」とニッコリ笑っているので実に憎たらしい。
第25段 憎きもの
・局(つぼね、私室)にこっそり忍んで来る恋人を見つけて吠える犬。
・皆が寝静まるまで隠した男がイビキをかいていること。
・大袈裟な長い烏帽子(えぼし)で忍び込み、慌てているので何かに突き当たりゴトッと音を立てること。
簾(すだれ)をくぐるときに不注意で頭が当たって音を立てる無神経さ。
・軽い障子でさえガタガタ鳴らす男。
第26段 胸がときめくもの
・髪を洗い、お化粧をして、お香をよくたき込んで染み込ませた着物を着たときは、別に見てくれる人がいなくても、心の中は晴れやかな気持ちがして素敵だ。
・男を待っている夜は、雨音や風で戸が音を立てる度に、ハッと心がときめく。
第27段 過ぎ去りし昔が恋しいもの
・もらった時に心に沁みた手紙を、雨の日などで何もすることがない日に探し出した時。
第93段 呆然とするもの
・お気に入りのかんざしをこすって磨くうちに、物にぶつかって折ってしまった時の気持ち。
・横転した牛車を見た時。
とても千年前に書かれたとは思えない。
心の動きが現代の私たちと何も変わらない。
描かれたのは、冗談を言い合い、四季の景色を愛で、恋話に花を咲かせる女たち。
そこには敬愛していた定子を襲った悲劇は一言も書かれていない。
作品中の定子は、常に明るい光の中で笑っており、
『枕草子』そのものが彼女への鎮魂歌となっている。
清少納言は、
自分の人生を、
出会った自分の愛する人々を引き連れて、
筆を通して永遠に導いた。
清少納言に限らず、
こういった才能を持つ偉人たちを羨んで止まない。 2011-10-20 谷澤