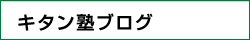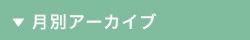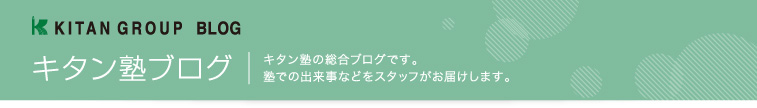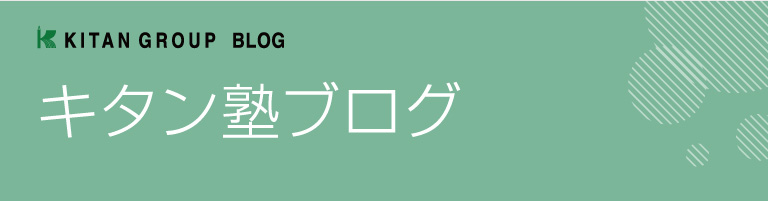毎年、秋のこの時期(体育の日の前後)は塾は休みにさせていただいています。今回は祝日も含め、来週の前半は連休になります。ほかの学年のみなさんは、定期テストの準備をそろそろしようかな・・・くらいの時期なので、結構この連休は楽しみにしているかもしれません。
しかし、中3受験生はなかなかそうも言っていられない時期ですよね。
先日、高校入試説明会を行いました。それで少しでもやる気が出たみなさん、あの資料に書いてあった、「高校入試のための究極の勉強方法」(といっても特別なことではありません。当たり前のことを積み重ねて・・・と言っているだけです)を、この連休からはじめてみませんか。
中林先生から、「第3回岐阜新聞テスト記録用紙」はもらいましたか。まずは、「高校入試の手引き」を引っ張り出し、20年度、21年度、22年度の「第3回岐阜新聞テスト」を、「入試のためのサンドイッチ式勉強法」の手順にしたがって、やってしまいましょう。
もうやりはじめてますって? そりゃあすごいですね。それ以外にすることはないですかって。
ありますあります。水曜日の週テストはしっかりやり直していますか。英語、数学とも完璧にやり直してほしいのです。
英数の週テストを採点していて、気づいたことを書き溜めていたので、その文章を載せておきます。復習するときの参考にしてくださいね。
第2回英数週テストのコメント
まず、英語の英作文、大問②について。こうした、自由に書いていい英作文は、まず、問題の条件をよく確認してから書き出すこと。今回の場合、問題の条件に、問1→2文で自由に書きなさい。ただし、1文の語数は5語以上とし、ピリオドやコンマなどの符号は語数に含めないものとする。問2→紙の使用についてあなたが心がけたいことを、2文の英語で書きなさい。という条件がついていました。
当然、問1で1文しか書いてない。1文の語数が4語しかない。などは点数になりません。問2でも、1文しか書いてない場合はダメですし、「紙の使用について」となっているので、紙についての記述が全然ないのもダメです。
また、紙=paperは、数えられない名詞です。Many papersとはいいません。あくまでMuch paperです。A piece of paper, two pieces of paperという言い方はあります。
また、よく聞く言葉で、リサイクルという言葉がありますが、「recycle」というつづりになります。つづりを間違えたら、点数にはなりません。また、この単語は「動詞」です。「do recycle」ではなく、「recycle」だけで「リサイクル(再利用)する」という意味になります。名詞なら、動名詞にして、recyclingとなります。
そして、この問題があっていた人も、書いたけれど違っていた人も、全然書けなかった人も、必ずやってほしいことがあります。それは、模範解答をそのまま、最低3回は写してみてほしいということです。模範解答がどのくらいのレベルの英文を書いているのか、どのくらいの長さの英文を書いているのか、そうしたことを、実際に手で書いてみて、体験してほしいのです。
こうしたことを続けることによって、「自由英作文」「条件英作文」に強くなることができます。
次に数学です。まずは、大問④の問1を見てください。書けましたか。そして、書いた答案はあっていましたか。書けたつもりになっていても、意外と○がもらえてないということはありませんか。この証明は、教科書や塾のテキストに何回も登場する、基本中の基本とも言える証明です。ということは、完全に書けていないと○がもらえないということです。合同までの証明はほとんどの生徒が書けているのですが、そのあとがまずい。2等分のみ書いてあって、垂直の理由に触れていなかったり、逆に、垂直のみ書いてあって、2等分の理由に触れていなかったり。また、垂直の理由は、模範解答の通りでなければなりません。もう一度、英語と同じく、模範解答を丸写ししてください。
大問②の問2では、せっかく答えがあっているのに、○があげられない答案がありました。それは、式を「簡単な式に直して」書いてある答案です。この場合、片方の式はもともと簡単なのでよいのですが、もう片方の式は、そのまま方程式をたてると、相当複雑な式になったはずです。それをわざわざ簡単な式に直す必要はなく、この場合だと、直して簡単にした式には○があげられません。
以上のことを踏まえて、もう一度答案を見直してください。
第3回英数週テストのコメント
先週の英語、1の問5→It is easy for a kite to find something to eat from here.は、今後必ずできるようにしておこう。「a」の位置が変な人が多かったです。問6は、質問文がbe going toなので、答えもbe going toにするのが原則だと思いますし、昔はそうでなければ×にしていたのですが、最近は、be going toで聞いても、未来の文(will)や勧誘の命令文(Let’s)であっても、文脈が良ければ使うため、それでも正解にしました。
2の問3は迷った答案が多いです。まず、grillig fishやboiling fishは変です。焼いている魚、煮ている魚となってしまうからです。あくまで魚は、焼いたり煮たりされるものであるから、grilled fishやboiled fishが正しい。I want to try to eat fish.なんて表現も多かったのですが、want toやtry toは、同じような使い方をする表現なので、同時に使うことはなく、I want to eat~.やI try to eat~.のどちらかにするべき。迷ったのは、①I want to try grilling [boiling].や②I want to try grilling[boiling] fish.という表現。実はtryには、try~ing(試しに~してみる)という表現があり、だとすると、①や②は、「試しに焼いて(煮て)みたい」となって正しいことになってしまう。さらに調べると、grillやboilは他動詞と呼ばれ、目的語が必要(正確にはどちらも自動詞として使えるが意味が変になってしまう)な単語なので、文法的には、①はまちがいで、②が正しいことになってしまう。すると、さきほどgrilling fishやboiling fishはまちがいと言ったが、②の表現のときだけは正解になってしまう。というわけで②を書いた人は正解にしたが、そこまでわかって書いているとは思えなかった。まあ、そう表したいなら、I want to try grilled[boiled] fish.とするのがいいと思います。
さきほど、他動詞・自動詞ということばが出てきました。さきほどの例はわからなくもいいのですが、3の問4⒝のときは、They joined it last October.のitを落としてはいけない。本文から考えると、They joined the Great Buddha ceremony at Todaiji Temple last October.の下線部をitにしたと思えばよい。They joined the ceremony last October.は迷って○にしたが、あまりすっきりしない。この場合、last Octoberがメインの答えなので、その他はなるべく軽くするのが原則です。
先週の数学は、4の問1の証明に関して言えば、書いた人はだいたいあっていた。ただ、時間が足りなくて、そこまでたどりついていない人がほとんど。また、その問題の問2もできていない。問1で合同を示したのはなぜかをもっとよく考えてみよう。平行四辺形の面積を求めるかわりに、△ABFの面積を求めることにまず気づくこと。あとは、△AHFが、1:2: √3の三角形であることに気づけばできます。
2はほぼ全滅。3と5と6もあまりできていません。過去の先輩も同じテストを受けてきたが、ややさびしい印象があります。昨年の先輩のほうが、もう少し、スピード(馬力といってもよい)があったような気がします。
数学は、ふだんはじっくり考え、ゆっくり取り組むことも大切なのですが、テストのときは、もう少し、気持ちにもっとエネルギーを入れて取り組んでほしい。馬力の入れ方で、20点くらい違ってきます。このテストは、そうした部分を鍛えるテストだということを、もう少し認識してほしい。
第4回英数週テストのコメント
相変わらず、英語の作文のミスは多く、数学の馬力が足りない。
英語は決まりがある言葉だ。複数形のs 三人称単数現在のs そうした基本中の基本を忘れる。時制(過去形・現在完了形・現在形・未来形)をまちがえる。目的語のいる動詞(他動詞という)なのに、動詞のあとに何もつけていない。基本的な英語のつづり字がちがっている。基本的な英語の順番がちがっている。こうしたミスは、知らなかったというよりは、テスト時間中の真剣さが足りなかったというべきだ。
数学は馬力が必要だ。それはスピードを速くするとか、がむしゃらにやるとか、そういうレベルの話ではない。目の前の問題に対して、瞬間的に、「これは自分が機械的に解ける問題か、考えないといけない問題か」「機械的に解けるとして、どの方法で計算するとベストな問題か」「考えて解けそうか、考えても時間がかかりそうか」「どの順番で取り組めばこのテスト問最の正解数が上がるのか」といったことを判断し、テスト時間中、心がおれずに最後まで集中する。それには、やはり真剣な態度でテストに向き合う必要がある。
第5回英数週テストのコメント
≪英語≫
Most of the things「そのものの大部分」←sold there「そこで売られている」(過去分詞の形容詞的用法) ここまでが主語。そこで売られているもののほとんどは中古品です。
「その内容にあたる一文を本文中から見つけて、その文の意味を日本語で書け」「その理由にあたる最も適当な一文を、その男の人が言ったことの中から見つけて、その文の意味を日本語で書け」と聞かれたら、「~ということ」「~だから」と答えてはいけません。あくまでも、見つけた英文を訳すだけの命令なのです。
「watch」というのは、「じっと見る」「凝視する」よって、テレビで見たり、鳥を観察するときに使います(bird watchingとかいうよね)。それに対して、「see」はこちらから見ようとしなくても「目にとびこんでくる」という感じです。そうすると、例えば野球場などは、こちらが見ようとしなくても、「自然に目に入ってくる」という感じがわかるでしょう。
「at[to] Sakura Station」と「at ten in the morning」を逆にしている人がいます。どこのテストの解説だったかは忘れましたが、英語の解説で、「in the seaとin summerのように、『場所』と『時間』に関する語句では、『場所』を先に表現します」とした記憶があります。
「bring(持ってくる)」と「take(持っていく)」は微妙で、この場面なら、「take」もありかな…という気もしましたが、やはり問題文に「持ってくる」と書いてある以上は、その指示に従うべきでしょう。
≪数学≫
0≦y≦8をまちがえた人は、大反省すべきでしょう。高橋先生の授業で習っているはずです。問10の説明は、1gあたり、または100gあたりにそろえるのがよいでしょう。なぜか理由があっているのに、肝腎な記号が違っているのには笑えました。
ⓐ (12−x)2=100 がおおもとの式で、それを変形していくと、ⓑ 144−24x+x2=100 さらに整理するとⓒ x2−24x+44=0 となります。この場合、二次方程式としては、最初の㋐を書くべきで、整理した式はⓒです。あくまでも、ⓑは途中の中途半端な式であることを理解してください。
証明は、難しかったにもかかわらず、数人の子が挑戦し、そのうち2人が完全な答案を書ききったことは非常にうれしかった。
まだまだ、せっかくあっているのに、約分をしていないという、基本的なミスもめだちました。もったいないですね。
今回は、英語も数学も、「なんとかしよう」という気迫のようなものを感じる答案が、数多くありました。この調子でがんばってください。
わからない問題を、1つも残さないように。どうしてもわからない問題が出てきたら、必ず光の泉のスタッフをつかまえて、納得できるまで質問してください。この前の誰かのように、1人の先生に聞いてみたけれど、よくわからず、もう1人の先生に聞いてみる…くらいのファイトは大歓迎です。
「本文にそって日本語で書きなさい」という問題の「基本中の基本」は、答えの場所の英文を探し、それをていねいに訳すこと。例えば、1の問1なら、「I want a lot of friends, but I’m afraid I can’t get along with other people.」をていねいに訳し、「という問題」で終わればよい。問2なら、「If you smile and look friendly, it’s easier for them to talk to you.」をていねいに訳し、「から」をつければよい。例えば、問1なら、この原則にそって答えを作ると、模範解答以外ありえない。問2は、「friendly」を「フレンドリー」と訳した答案に迷った。これは訳したことになるのかどうか、これを書いた人は一度考えてほしい。実際は○になる場合もあるかと思ったが、あえて☓にしました。「talk to / speak to」が「~に話しかける」、「talk with / speak with」が「~と話す(話し合う)」の部分も大切。
同様に、4の問2も、「Now, English is ~ learning and using it」「So we don’t ~ besides English.」の2文に理由の1つが書いてあり、「It takes much time ~ practice.」「So there is ~ another English.」の部分に理由の2つめが書いてある。どちらも決め手は「So」の存在である(1つめは『Now』も決め手になる)。この部分以外ありえないというのがわかりますか。
1の問5では、「直人のメール」に返事を送る問題なのに、「返事のメール」にさらに返事を送っている勘違いがめだちました。4の問3では、「language」が数えられる名詞だから、「other languages」または「another language」としなくてはならないのに、「s」のつけ忘れなどがめだちました。「another」が、「an」「other」からきたことばであることはわかっていますか。これも大切です。どちらにしても、この2つは「ミス」でしょう。
≪数学≫
そろそろ、1は全問あっていてほしい。ほとんどの人がそれはクリアできるようになってきたのは嬉しい。1問でもまちがえた人は、反省してきちんとしておこう。
2で、特に問2に注意。グラフの概形はあっているのですが、ななめの直線を入れるとき、少しずつずれていて、○にできない答案が目立ちました。こうした点取り問題で落とすのは、入試を考えると非常にマイナスです。問3で、「x≧150のとき」という条件を見落とした人もそうです。これは絶対に落とせない問題。x≦150のときなら、y=ax+400とおいて、x=150, y=1300を代入し1300=150a+400 150a=900 a=6よりy=6x+400 こちらを書いた人が非常に多い。これは明らかに問題の読みまちがいです。y=6x+400とy=1000の交点で、x=100が出ます。B社のx≧180のとき、y=8x+bにx=180, y=1000を代入して1000=1440+b b=−440 y=8x−440とy=5x+550から、3x=990からx=330 すべてたいした計算ではなく、基本的な計算の積み重ねでできます。決して難しい問題ではありません。
5は、問1も問2もまああまあの難問です。問1の⑵では、赤い台形の上に必ず黄色い台形があり、その差は、⑴の答えと同じく、4cm2になる。一番上に赤い三角形があることに注意すると、赤い台形や黄色い台形は全部でn−1個ある。赤い図形-黄色い台形=赤い三角形+赤い台形-黄色い台形=2×2÷2+4(n−1)=2+4n−4=4n−2
問2では、⑴と⑵ができて⑶ができない(または時間が足りなくてそこまでいってない)パターンが多い。しかもその大半が、「太郎さんが勝った」と解釈して、3a+10=30−3a+10の式しか書いてないケースがほとんど。「花子さんが勝った」とすると、30−3a=3a+10+10となり、このときはaが分数となる。結果的に「太郎さんが勝つ」ことにはなるのだが、「花子さんが勝つ」場合も調べ、それがだめなわけまで書かなければ、途中の式には○があげられない。
実はこの文章は、昨年、テストごとにコメントしていたみたいで、「第4回」のコメントが短いのは、このとき、お葬式があったということみたいです。昨年のものなので、今年と多少採点基準がちがっていたらごめんなさい。しかし、だいたいの観点は合っていると思うので、復習には十分役に立つでしょう。
中3の生徒は、この文章をプリントアウトするなりして、第2回~第6回までのテストを、もう一度やり直してみましょう。どれも岐阜の公立高校を意識して作った問題ばかりです。これも「サンドイッチ式」に徹底して復習するとよいですよ。
実はこの週テスト、国語や理科や社会も作ってあります。休み明けくらいに、国、理、社もやってみましょうか。2週間かけて、5教科終わらせることもできます。だんだん、公立入試に近い形でやっていきましょう。
では、この休み期間、自分の勉強方法の確立に、全力を尽くしてくださいね。